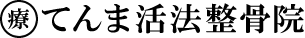大阪市北区松ヶ枝町1-41
- ホーム
- てんま活法整骨院の治療コラム
- 春のストレスが肩こりに出る?職場の環境変化と体の不調
春のストレスが肩こりに出る?職場の環境変化と体の不調
最近、肩こりがひどくなった気がする
毎年、春になると頭痛や体のだるさが出る
そんなふうに感じている方はいませんか?

はじめに
こんにちは、大阪市北区てんま活法整骨院の木下です。
特に20〜30代の女性に多いのが、春先の気候や環境変化による肩や首のこり。
厚生労働省の「令和4年国民生活基礎調査」によると、女性の自覚症状で最も多いのが肩こりです。
特に気温差・仕事環境の変化・新しい人間関係など、春は無意識のうちにストレスを溜めやすく、体のあちこちに不調として表れる時期でもあります。
本記事では、春に起こりやすい肩こり・首こりのメカニズムと、姿勢や生活習慣との関係、そして今日から実践できる対策について詳しく解説します。
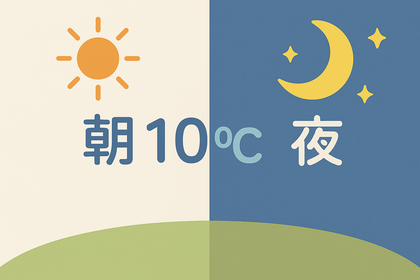
原因解説
春先に肩こり・首こりが増えるのは、精神的・身体的ストレスが複雑に絡み合う季節的特徴にあります。
以下に、主な原因をより専門的に詳述します。
■ 精神的ストレスと交感神経の過活動
春は入社・異動・転勤・引っ越し・人間関係の変化など、生活環境が一気に変わる時期です。
これに伴って生じる心理的ストレスが、体の緊張樹体をコントロールする交感神経を活性化させます。
交感神経が優位な状態になると、以下のような生理反応が起こります
- 心拍数の増加
- 呼吸数の増加(浅く速くなる)
- 血管収縮による末梢循環の低下
- 筋肉の緊張上昇
特に首や肩周囲の筋肉は、交感神経優位時に収縮しやすく、その持続によって筋疲労・血行不良を招き、肩こりの一因となります。
■ 新しいデスク環境による姿勢不良
職場や在宅勤務の開始などで、椅子や机の高さ、ディスプレイ位置が変わることがよくあります。
これにより、首を突き出した姿勢を取りがちになります。
この姿勢では、頭部の重量(約4〜6kg)を支えるために、首の後ろ側の筋肉が過緊張します。
猫背姿勢になり、胸が圧迫され、呼吸が浅くなる
といった複合的な負担がかかり、慢性的な肩こり・首こりを誘発します。
■ 昼夜の寒暖差と自律神経の乱れ
春は1日の中での気温差が大きく、服装や体温調節が難しい時期です。
自律神経は体温維持に大きく関与しており、この温度変化への適応負荷が交感・副交感神経のバランスを崩す原因となります。
自律神経が乱れると
- 血流の制御が不安定になり、筋肉への酸素供給が減少
- 冷えによる筋緊張が強まり、回復が遅れる
- 睡眠や消化機能にも悪影響が出て、慢性的な疲労が蓄積
その結果として、首肩まわりの筋肉に老廃物が滞留しやすくなり、コリや痛みが強く出やすくなるのです。
■ 呼吸が浅くなることによる筋緊張
ストレス状態では自然と胸式呼吸が中心になります。
このとき、肋骨を持ち上げる動きに関与する筋肉が過剰に使われるため、特に首の前側〜肩の上部の筋肉に慢性的な負荷がかかります。
また、浅い呼吸が続くと酸素摂取効率が低下し、全身の代謝活動も低下します。
これにより疲労物質が蓄積しやすくなり、筋肉痛・重だるさ・締めつけ感が強くなります。
■ 睡眠の質の低下と疲労回復の遅れ
体の疲労が回復するのに睡眠はとえも重要です。
- 環境変化による生活リズムの乱れ
- ストレスによる脳の覚醒
- 夜間のスマートフォン使用による眠りの質の低下
このような要因で睡眠の質が低下するとホルモンの分泌が減少し、筋肉の修復・疲労除去がうまく進みません。
結果として
- 起床時から首肩が重い
- 疲れが抜けない
- 頭痛や集中力低下
などの二次症状も出やすくなります。
こうした負のスパイラルが肩こりを慢性化させる要因となります。
■ ホルモンバランスの変動
女性の場合、春のストレスはエストロゲンやプロゲステロンといった女性ホルモンのバランスにも影響します。
これにより血管拡張・収縮、免疫反応、情緒の安定などが不安定になり、体がむくみやすく、筋肉がこわばりやすくなるという特徴があります。
PMS(月経前症候群)や月経周期による体調変化も、肩や首まわりの不調に拍車をかけることがあるため、女性特有の生理的リズムも考慮したケアが重要です。
以上のように、春に起こる肩こり・首こりは単なる姿勢や筋肉の問題ではなく、自律神経・呼吸・ホルモン・睡眠など複数の生理システムの乱れが背景にあるのです。
だからこそ、運動やストレッチだけでは根本改善が難しく、生活習慣と体の使い方の両面からの見直しが必要になります。

体のゆがみの解説
肩こりや首こりの背景には、姿勢の崩れや動作のクセが密接に関係しています。
例えば、右利きの方がパソコンのマウスを右手で操作し続けると、肩の高さや筋緊張の左右差が生まれ、首から背中にかけてアンバランスな筋活動になります。
また、精神的な緊張状態にあると、肩が自然にすくんだり、猫背気味になったりといった姿勢を取りやすくなります。
それが持続することで首や肩へのストレスが蓄積します。
このような習慣が続くと、首や背中をうまく使うことができず、筋肉だけでなく関節の動きも制限されてしまいます。
結果として、肩こりや首こりが慢性化し、頭痛や吐き気を伴うケースも見られます。
なお、骨盤が歪んでいるから不調が出るといった言い回しがありますが、骨盤そのものがゆがむわけではありません。
実際には筋肉のバランスの崩れや関節の使い方の偏りがゆがみとして姿勢に表れるものです。
体の構造上、骨盤が単独で変形することはありません。

対策
春の肩こり・首こりを根本的に軽減するには、単に揉んで楽になる対症療法ではなく、なぜ筋肉がこるのか?という原因へのアプローチが不可欠です。
以下に、日常生活で注意すべき具体的なポイントを専門的に解説します。
■ 1時間に1回の姿勢リセット
・筋緊張の持続を断ち切る
長時間同じ姿勢を取り続けると、同一の筋肉に負荷がかかり、筋肉内の血流不足が起こります。
筋疲労・炎症・痛みなどを感じる組織が過敏になり、コリや痛みを引き起こします。
対策ポイント
タイマーなどをセットし1時間ごとに軽く立ち上がる
肩の上げ下げを軽く3〜5回
肩の脱力、姿勢と血流のリセットをする習慣を意識しましょう。
■ デスク環境の最適化
・重心のズレを予防する
PCモニターが低すぎると首が前に出てしまい、頭の重さ(約5〜6kg)がそのまま首〜肩にかかります。
1cm前に出るごとに、首にかかる力は倍増するとされ、これが肩こりの原因に。
対策ポイント
モニターは目線の高さに調整
椅子の高さは、肘が90度で机に乗るように調整
背もたれと腰の隙間にクッションを挟み、骨盤を立てる意識をもつ
結果として、耳・肩・股関節が一直線に並ぶ理想姿勢に近づきます。
これは筋緊張の偏りを予防する基本姿勢です。
■ 呼吸の質を意識する
・横隔膜の活用
現代人の多くは無意識に胸式呼吸になっています。
これでは首肩の筋肉に過剰な負担がかかります。
ゆっくりとした腹式呼吸により、横隔膜の上下運動が内臓を刺激して、自律神経の安定・筋肉の弛緩に繋がります。
対策ポイント
椅子に座り、背もたれに軽く寄りかかる
鼻から4秒吸ってお腹をふくらませ、口から8秒かけて吐ききる
1日3セット、朝昼晩のルティーンにする
呼吸の質を上げることは、自律神経の安定と深い睡眠にもつながる体の再起動スイッチです。
■ 夜のルーティンを整える
睡眠の質を上げる工夫
浅い睡眠は筋疲労の回復を妨げ、緊張状態を強化します。
ポイントは、脱力してリラックスした状態で寝れるかです。
対策ポイント
就寝90分前までに38〜40℃の湯船に15分浸かる
体の深部体温を一時的に上げ、その後下がる際に眠気を促進されます。
就寝1時間前からスマホ・PCはオフ
深部体温の調整と光刺激の遮断は、睡眠に関わるホルモン分泌を促し、深い睡眠の獲得につながります。
まとめ
春は新しいスタートの季節である一方、心と体に知らぬ間に負担をかけやすい時期でもあります。
特に肩や首の不調は、ストレスが溜まっているよ、無理していない?という体からのサインかもしれません。
無理に我慢せず、生活を少し見直すだけで、体は確実に変わっていきます。
長年、体の緊張状態つづいて、大きく体がゆがんでいる方も多くおられます。
今回お伝えした対策をしたけれどあまり変化が感じれない方は、大きく体がゆがんでいるかもしれません。
その際は体のゆがみを整える専門的な施術が必要となります。
国家資格を持った専門院へご相談ください。
当院でも体のゆがみから症状へアプローチをする施術を行なっております。
お困りの際は一度ご相談ください。
関連エントリー
-
 手首、指の痛み〜これって腱鞘炎?
「スマホを触ってと重だるさを感じる」「料理中に包丁を握るとズキンと痛む…」そんな違和感が続いているなら、もしか
手首、指の痛み〜これって腱鞘炎?
「スマホを触ってと重だるさを感じる」「料理中に包丁を握るとズキンと痛む…」そんな違和感が続いているなら、もしか
-
 マラソンでの膝の痛み〜ランナー膝・腸脛靱帯炎〜
「走り始めは問題ないのに、途中から膝の外側がズキズキしてくる」「練習後は落ち着くけれど、次に走るとまた同じ場所
マラソンでの膝の痛み〜ランナー膝・腸脛靱帯炎〜
「走り始めは問題ないのに、途中から膝の外側がズキズキしてくる」「練習後は落ち着くけれど、次に走るとまた同じ場所
-
 口を大きく開けれない〜顎関節症の原因と対策を解説〜
「朝起きたときから顎が重だるい」「口を開けるたびに、顎がズキッとする」このような症状でお悩みではないですか?[
口を大きく開けれない〜顎関節症の原因と対策を解説〜
「朝起きたときから顎が重だるい」「口を開けるたびに、顎がズキッとする」このような症状でお悩みではないですか?[
-
 朝起きたら頭が痛い〜頭痛のタイプと原因を解説〜
朝から頭が重くて、一日がつらい」検査では異常がないと言われたけれど、不安は残ったまま…そんな頭痛を抱えながら、
朝起きたら頭が痛い〜頭痛のタイプと原因を解説〜
朝から頭が重くて、一日がつらい」検査では異常がないと言われたけれど、不安は残ったまま…そんな頭痛を抱えながら、
-
 気温差で起きる頭痛、寒暖差の大きいこの冬は要注意
今年の冬は頭痛が出やすくなった気がする毎年、冬になると、なんとなく頭が重い日が増える寒くなってから頭痛の回数が
気温差で起きる頭痛、寒暖差の大きいこの冬は要注意
今年の冬は頭痛が出やすくなった気がする毎年、冬になると、なんとなく頭が重い日が増える寒くなってから頭痛の回数が
てんま活法整骨院
まずはお気軽にお問合せくださいね。
電話番号:06-6352-7800
所在地 :大阪市北区松ヶ枝町1-41
JR東西線 大阪天満宮駅より徒歩6分 地下鉄南森町駅より徒歩8分
営業時間:平日 9:00〜21:00
土曜 9:00〜18:00
休診日:木曜日・日曜日・祝日